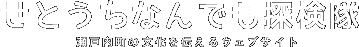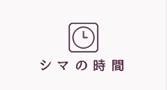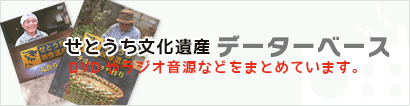鹿児島地方気象台によると、5月15日(水)に奄美地方が梅雨入り。平年より4日、昨年より2日遅いとのこと。
平年の梅雨明けは6月29日頃。
あと、1ヶ月は、雨模様が続くのかな?
人間にとってはちょっと憂鬱な雨も、植物にとっては恵みの雨。
潤いに満ちて、生き生きとしています!!
今回は、シマの梅雨時期の花たちをご紹介!
ゲットウ

梅雨時期の代表的な花「ゲットウ」
シマでは「サネン」の呼び名で親しまれています。
フチモチを包むなど、シマの生活に欠かせない植物です。
クマタケラン

ゲットウに似ていますが、こちらは花が上に伸びます。
こちらも、フチモチを包みます。
「ムチガシャ」とも呼ばれ、サネンよりこちらの方が良いとも言われます。
ゲットウとクマタケランの違いは、花の咲くこの季節が一番分かりやすいかも!
イジュ

こちらも、昔からシマの生活に欠かせない大切な木。
白アリに強いことから、高倉の柱など建築材に使われました。
また、樹皮は魚を獲る(魚毒)のに使われました。
オオバナチョウセンアサガオ

シマでは園芸名の「ダチュラ」と呼ばれることが多いです。
田中一村も描いていますね。
チョウセンアサガオ属は、「曼陀羅華」と呼ばれ、鎮静麻酔薬として使われていたことも。
小説『姑獲鳥の夏』では、媚薬の原料として登場しています。
クチナシ

果実は、食品の黄色色素に使われました。
果実が熟しても口を開かないことから、「口無し」と名付けられたとか。
コンロンカ

中国の崑崙山に降り積もる雪のようだ、と言うことで付けられた名前。
昔の人の名付けのセンスは、抜群ですね。
シマでは「ワラベナカシャ(童泣かしゃ)」と呼ばれています。
このツルを使って山で薪を縛ろうとしても、すぐ切れてしまうことからついた名前とか。
こちらは、センスも教訓も素晴らしい!!
白く見えるのは萼片(がくへん)で、黄色い星のような部分が花です。
隊長鼎は、これらの白い花を見かけるようになると、もうすぐ梅雨だなぁと思います。
山々にひっそりと白い花咲く、梅雨。
時折、足を止めて、梅雨時期に咲く花を愛でたり、雨を眺めてゆったりと過ごすのもいいですね。
< 参考文献 >
・『 琉球弧・野山の花 from AMAMI 』 片野田逸朗著 大野照好監修
2013.5.17 瀬戸内町
S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会) 隊長鼎
鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内